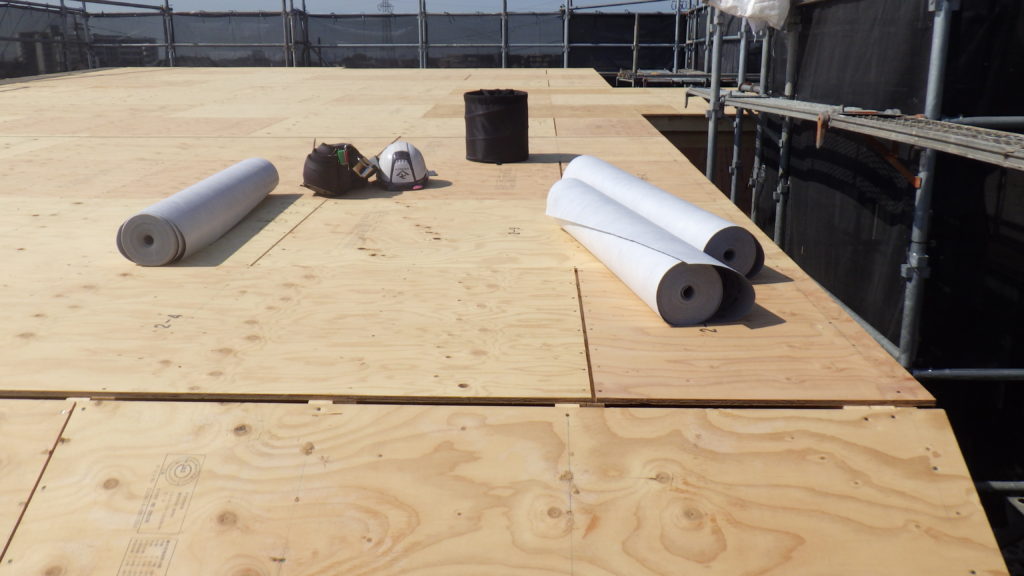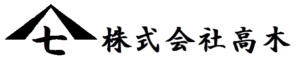雨といなんて、普段おそらく全く気に止めないものだと思います。
台風や大雪などで雨といが外れたり落ちたりという被害が出ると急に気になりだす。そんな部品だと思います。
雨といも何社か製造メーカーがあり、その中でもサイズや形状様々あります。
よって一口に「角型の雨といなんだけど・・・」では材料屋さんも困ってしまいます!
各社カタログとにらめっこも良いですが、廃盤品だったりするとどこにも見つからずに廃盤かどうかの判断もできません。
ですので、プロの板金職人さんもそういった情報をしっかり持った建築板金資材のプロショップに相談するのが常套です。
それではどのようなポイントを押えた資料を持ち込むと、建築板金資材のプロショップが判断できるのか考えてみましょう。
写真を撮る

雨といメーカーを端的に調べるには竪樋の継ぎ手部材を観察してみてください。
特徴的なロゴやサイズが書いてあります。
上の写真はDenkaというメーカーのものです。軍配マークが目印ですね。竪樋55Φ用の100°のエルボだとわかります。
積水化学工業のものは’S’-lon、パナソニックのものはPanasonicまたはNationalと書いてあります。
この3社が塩ビ雨とい市場のほとんどを占めていますのでここを抑えておけば大丈夫です!
軒樋(横樋)の場合は「止り」部材を撮影してください。
この形状で軒樋の種類がわかります。

上の写真はパナソニックのパラスケアU105というものです。
各社似たような形状のものを出していますので、なるべく高精細な写真があると判明が早いです。
また、同じメーカーでも同じ形状でサイズ違いというものもあります。
例えばDenkaのダンラインエクセルDL55とDL75、パナソニックのシビルスケアPC50とPC77です。
この場合は竪樋の径で大方判断できますので、合わせて提示すると良いでしょう。
ただし、径を絞る部材(例えば75Φから60Φなど)もありますので、それが使われていないことが前提です。
落とし口(じょうご)の形状も判断材料となります。
サイズを測る
竪樋の継ぎ手が見当たらない場合、方形屋根で止り部材が無い場合、じょうごではなく軒樋に穴をあけてドレンで竪樋に落としている場合など、判断材料に乏しいことがあります。
手元に写真を撮れる器材が無い場合もあるでしょう。

軒樋の寸法をもし測れるようであれば、上の図のような部分の寸法を細かく調べるとわかります。
せめてA,B,Cの寸法がわかれば大きなヒントになります。
取り付け方を伝える
軒樋の吊金具にも種類・寸法があります。
軒樋の表面で受けるように留める金具を「受け金具」または「外吊り金具」といいます。

対して、軒樋の水を受ける側・内側で吊る金具を「内吊金具」と呼びます。

半月型の雨樋で内吊りというのはほとんど無いです。
塩ビではなく鋼板雨といでは内吊りで納めるものがあります。
また、吊金具自体の建物への留め付け方にも種類があります。
破風の表面にビス留め付けをする「面打ち」

和風建築などに多い、屋根垂木が軒先に出ているタイプのもので、垂木に釘のように打ち込むものを「打ち込み」
垂木の横に釘留めするものを「横打ち」といいます。

特に上の写真のような純和風な建築の場合、意匠性であったり垂木と屋根面の高さに合わせて「ニカド」「ミカド」「ツル首」など吊金具の形状がたくさんあります。
以下にその一部の一覧表を貼り付けておきます。

まとめ
いかがでしたでしょうか。
あまり気に留めてもらえない(笑)雨といにも色々なポイントがありますね!
基本的に雨樋は、軒樋は軒先に、竪樋は外壁の角に付きますので、雨仕舞の他に建物の輪郭線のような役目もあります。
他にも窓のサッシや壁の下側と基礎の間に取り付ける土台水切りも同じような効果があります。
しかし例えば、近年では外壁が上下ツートンになっていたりすると、その色に合わせて竪といの色も上下ツートンにするなど、「それはどうなんだろう?」という案件もあります。
壁に対して当然少し飛び出しますので、水平位置から見るとキレイにツートンになっていても、足場が外れて地上から見ると下の樋の色がモッコリと上の壁の色に飛び出してきますので、正直良い仕上がりだとは思えません。
樋・サッシ・土台水切りの色を合わせることで一貫性が保たれ美しい佇まいになる、というのが伝統的なやり方なのですが、考えが保守的すぎるのでしょうか(^^;
参考になりましたでしょうか。
ご意見・ご感想ありましたらメールなどお願いいたします。
いいねボタンやSNSシェアなどしていただければ幸いです。