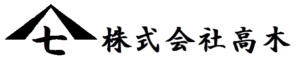代金未払い最終回、回収手続きの続きです。
3.一般的な回収手続きⅠ(続き)
(3)中立な第三者に間に入ってもらう方法
単純に、資金繰りの事情等で未払いが生じている今回のリーディングケースではあまり効果的ではないかもしれませんが、事実関係に争いがあるような場合(例えば、追加工事の範囲についての争いがある場合等)等に、交渉で進展が無い場合、いきなり裁判に持ち込むのではなく、「裁判外紛争解決手続(ADR)」という方法を使える場合があります。
ADRには様々な手続きが含まれるため、一言で説明するのが難しいのですが、まず日本語のとおり理解していただくと、そのまま、「裁判以外の方法」で「紛争」を「解決」するための手続きの総称をいいます。
裁判が、国の期間である裁判所によって争いごとの最終的な判断を付ける場であるのに対し、ADRは、中立な第三者の専門家に間に入ってもらいながら、裁判のようにはっきりと白黒をつけることなく、基本的には話し合いで解決を図っていくものになります。
解決結果に一定の効力があること等から、勝手に誰でもができるものではなく、国が認証を行った紛争解決機関がサービスを提供しています。
下請等の中小企業者が使えるADRとしては、全国中小企業振興機関協会が提供している下請適正取引推進センター(下請かけこみ寺)や、弁護士会の紛争解決センター等があります。
ADRのメリットは、裁判のように法律上決められた枠内での解決を超えた柔軟な解決が可能になること、概ね3か月程度の期間内で集中して手続きを行い、そこまでに結論を出すために、短期間で終了すること、非公開で行うことができること、手続き費用が無料~比較的安価に済むこと等が挙げられます。
他方、あくまで話し合いを元にするため、同意ができない場合にはそもそも手続きの開始ができない等、相手に強制をすることはできないものです。そのため、双方の隔たりが大きい場合には、時間が無駄になってしまう恐れもあります。
どういったことを実現したいのか、よく考えたうえで利用することをお勧めいたします。
(4)裁判による回収Ⅰ(訴訟)
裁判、特に訴訟手続は、最も強力な回収の手段です。
訴訟で主張が認められ、判決が出れば、相手の不動産や銀行口座を差押えて、強制的に換金・回収を行う事ができるようになります。
また、訴訟を進めていく中で、裁判官に間に入ってもらう形での話し合いの場が設けられる場合があります(訴訟上の和解)。
この場合、判決を行う裁判官が進行を行うので、通常の話し合いや民間ADR等に比べると、ある程度事実関係に争いがあっても合意に至りやすいと言えます。
他方、公開の手続きになること、裁判というだけで身構えられてしまい敵対的に捉えられることがあること、一定の費用がかかること、厳格な手続きを取るため場合によっては半年以上の時間がかかること等のデメリットもあります。
また、先方に換金可能な財産がない場合、せっかく勝訴判決を取ったとしても「絵に描いた餅」になってしまう可能性もあることも考慮に入れる必要があるでしょう。
(5)裁判による回収Ⅱ(保全手続き)
厳密には回収そのものを目的とする手続きではありませんが、裁判所に「仮の」判断を行ってもらう、保全手続きという手続きも、回収において重要な手段の一つです。
本来、差押え等、相手の財産を制限するためには、訴訟による判決を必要となります。
しかし、前述のように、訴訟では厳格な手続きの下、相手の反論等も踏まえて判断を行うため、一定の時間がかかってしまいます。
その間に、相手が財産を売り払ってしまったり、お金を使ったりしてしまえば、判決があったところで何も得るものがない、という事態も起こりかねません。
そこで、権利を主張する側が裁判所に対して一定の立証を行い、その権利の存在がある程度確からしいと認められた場合に、「仮に」差押えをし、財産を売り払うこと等を禁止することで、権利を保全するということが認められています。
もちろん、仮のものなので、例えば不動産を強制的に競売にかけるようなことはできず、あくまで勝手に処分してしまうことを禁じるだけですので、権利の実現には訴訟を提起することが必要になります。
しかしながら、この手続きを取ることで相手にこちらの意思を示し、心理的なプレッシャーをかけることで、事実上、相手の任意の履行を促す効果があります。
この手続きのメリットとしては迅速に一定の法律上の効果が得られる事が挙げられます。
他方、デメリットとしては、相手が争った場合には訴訟が必要になる場合があること、仮の判断が誤っていた場合に備えた担保金を用意する必要があるため、比較的多額の費用が見込まれることが挙げられるところです(担保金は問題がなければ最終的には戻ってきます。)。
4.まとめ
以上、未払い代金の回収という観点で、様々見てきました。
ご自身での回収を行う場合や、専門家に依頼する場合等に参考にしていただけると幸いです。
弁護士へご相談いただくことも、一つ、皆さまの助けになるかと思いますので、弊所にもお気軽にご相談ください。
特に今回の3.(3)~(5)は手続き面でも法律上の効果の面でも専門性が高く、弁護士の関与が必須になってくるところです。
但し、弁護士は、第3回で述べた通り、手段や見通しを示し、選んだものに対して最適な主張をしていくことはできますが、依頼者である皆様がどういった点を優先し、何を望んでいるのかということは教えていただかない限りわかりません。
お任せ、というのではなく、まずはしっかりとご自身の考えを伝えていただくことが必要です。その際にも、このコラムが一つの役に立てばと思います。
◎弁護士まかせにせず、どのように進めるのかきちんと話し合おう!